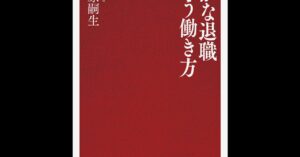こんにちは、たけもとです。
近年の働き方やライフスタイルの多様化に伴い、「静かな退職」という働き方が広まっています。
これは、最低限の仕事だけをこなし、会社に時間やエネルギーを注がず、プライベートに集中する働き方のことです。
従来の働き方とは真逆の指向となり、一見、消極的でネガティブなもののようにも思えます。
今回はこの「静かな退職」について、どのような働き方かや、この働き方を選ぶにあたって考えたいポイントについて解説します。
特に、現在30代前後の若手の方に向けて、考えたいテーマとして提示したい内容です。
はじめに:静かな退職とは?
「最低限の仕事」に徹する働き方
「静かな退職」とは、自分の仕事において、最低限の責務のみ果たす働き方のことを言います。
実際に会社を辞める…わけではなく、仕事に費やす時間やエネルギーを必要最低限に抑え、与えられた職務だけを淡々とこなす働き方を指します。

与えられた職務や責任範囲はきちんと果たしますが、それ以上の努力や貢献は行わない。
例えば、チームの目標達成に自分からは積極的に関わらない、自主的なスキルアップのための学習をしない、時間外労働を一切しない、親密な人間関係の構築を進んで行わない、といった行動が挙げられます。
今、「静かな退職」が注目される理由
近年、この「静かな退職」という言葉が急速に広まっています。
特に若手社員の間でこの「最低限の仕事のみに徹する」傾向が顕著に見られ、従来の「仕事に全力を尽くす」という価値観とは異なる、新しい働き方として注目されているのです。
それでは、なぜこのような働き方が広まっているのでしょうか。
その要因として、現代のライフスタイルやキャリア選択の多様化が挙げられます。
会社での仕事以外の、個人的な活動や関心領域、価値を見出せる分野が増えてきたことで、「仕事以外に時間やエネルギーを使いたい」と考える人が増えているのです。

仕事はあくまで生活の一部であり、すべてではないという考え方が、根強く浸透してきています。
仕事への情熱や達成感を追求するよりも、プライベートの時間を重視する。心身の健康やプライベートの充実を優先する。
これは、多様化する時代の中で生まれ、そして自然に受け入れられ、広まっている考え方と言えます。
若手社員に広がる「静かな退職」の背景
「静かな退職」について、特に若手社員にフォーカスを当てて、広まっている背景を考えていきます。
「静かな退職」が広まっている背景
ワークライフバランス重視の価値観
現代の若手社員は、上の世代と比較してワークライフバランスを重視する傾向が強いと言われています。
長時間労働や仕事中心の生活ではなく、プライベートの充実や自己成長のための時間を確保したいという意識が高まっています。
SNSの普及によって、他者の多様なライフスタイルに触れる機会が増え、従来の「当たり前」「普通」ではない生き方・働き方を多く目にすることになったことも、この価値観を後押ししていると考えられます。
燃え尽き症候群(バーンアウト)からの回避
過度な仕事へのコミットメントは、心身の疲弊や燃え尽き症候群(バーンアウト)を引き起こす可能性があります。
特に、新卒入社したばかりや、初めての転職を迎えた若手社員は、仕事への理想と現実のギャップに直面しやすく、早期に燃え尽きてしまうケースも少なくありません。
「静かな退職」は、そうした燃え尽きを未然に防ぎ、自身の心身の健康を守るためのいわば防衛策として選択されることもあります。
企業エンゲージメントの低下
企業に対するエンゲージメントの低下も、「静かな退職」が広がっている一因となります。
終身雇用制度が崩壊し、転職や副業が当たり前になった現代において、一つの企業に忠誠を尽くすという意識は薄れています。

そこで、今の会社でなく次の会社のための勉強や、自分自身のビジネス(副業)に時間を充てようと考える方は多いことでしょう。
また、企業のビジョンや目標に共感できない、自身の貢献が正当に評価されないと感じる場合にも、仕事への熱意を失って「最低限の仕事」に留まるようになることがあります。
「静かな退職」を選ぶということ
一見、仕事で働く量や熱意を抑えたこの働き方は、怠惰なもののようにも思えます。
しかし、単に「サボり」や「やる気のなさ」を意味するものではありません。
ライフスタイルや生き方が多様化する現代、一つの場所(会社)だけにエネルギーを注がない選択は、一つの戦略となっています。
仕事に注ぐ分の熱量や情熱を、趣味、自己啓発、家族との時間、副業など、仕事以外の領域に注ぎ、自分らしいライフスタイル、ひいては自分らしい生き方に繋げていくことができる働き方と言えるのです。

静かな退職のメリットとデメリット
それでは、ここで「静かな退職」のメリット・意義と、デメリット・課題を整理します。
メリット・意義
心身の健康維持とプライベートの充実
「静かな退職」の最大のメリットは、心身の健康を維持し、プライベートを充実させられる点にあります。

端的に、心の余裕と、時間が生まれるのが大きなメリット。
仕事のストレスから解放され、趣味や家族との時間、自己投資などに時間を費やすことで、精神の安定や自己成長に繋げられます。
目的意識を持って仕事以外の領域にエネルギーを費やすことで、やりたいことをする達成感、成長による自己実現を叶えられます。
キャリアの多様化とリスク分散
1つの会社に過度に依存しないことで、キャリアの選択肢を広げることができます。
例えば、空いた時間で副業を始めたり、新しいスキルや資格を習得したりすることで、本業以外の収入源やキャリアパスを築くことが可能。
変化の激しいVUCAの時代、一つの企業に縛られるリスクを分散して、様々な収益に繋がる柱を持つことで、キャリアの安定性を高めることにも繋がります。

デメリット・課題
キャリアの停滞と成長機会の喪失
会社での仕事への積極性がなくなることで、仕事での業績が残せなかったり、新たな経験を積む機会が減ったりして、キャリア成長が停滞する可能性があります。
特に、会社で本来手に入れられる可能性のあった、評価や昇進での給与の底上げ、仕事における専門領域のスキル習得が鈍化してしまうといったリスクも。
結果、十分なスキルがなく転職が思うように進められない、転職後も給与が低い、といったケースにも陥る可能性があります。
人間関係の悪化や孤立
仕事への関与度が低いと、周囲の同僚や上司からの信頼を失い、人間関係に亀裂が入ることがあります。
チームの一員としての協調性が失われ、孤立感を強めることにもつながり、結果、その会社での在籍が難しくなることもあり得ます。
そうなると、会社に居続けることへの心理的ストレスが増えてしまう結果に繋がり得ます。

「静かな退職」のやり方・留意点

自分のワークライフバランスのために、ぜひとも「静かな退職」をしたい!
…と思ったときにも、気を付けておきたいポイントを整理します。
責任感:与えられた業務は求められるレベルで遂行
「静かな退職」は、最低限の仕事に徹することですが、これは決して「無責任で良い」というものではありません。
この責任感を失ってしまうと、周囲に迷惑をかけるだけでなく、自身の信頼を失い、結果的に自身のキャリア全体にも悪影響を及ぼしてしまいます。
与えられた業務は、求められるレベルで遂行する責任があります。
目の前の仕事そのものには、集中して取り組むよう常に心掛けたいものです。
周囲の理解:コミュニケーションで認識合わせ
「静かな退職」を実践する上で、周囲とのコミュニケーションは非常に重要です。
会社では原則「組織」で活動する以上、自分の働き方や考え方を独善的に押し付けるのではなく、チームと仕事の分量や責任領域を協議して、仕事をする姿勢が求められます。
自身の業務範囲や限界を明確に伝え、双方で認識を合わせた状態で実践することが、好ましい在り方だと言えるでしょう。
目的意識:時間とエネルギーの使い方を決める
「静かな退職」を選択したとして、そこで時間とエネルギーを別の方向に使えないと、選んだことが裏目に出てしまいます。
上記のメリットを享受できず、ただただデメリットを被る、という形になってしまうのです。
具体的には、会社で得られる可能性のあるキャリアを捨て去る+人間関係の構築や成長の機会損失、という最悪のケースに。
仕事以外の何に時間とエネルギーを使いたいのか、しっかり自分の考えと決意を固めてから、「静かな退職」を実践しましょう。

「静かな退職」を学ぶためのおすすめ書籍
最後に、「静かな退職」という働き方についてより詳しく知りたい・考えたい方におすすめの書籍を紹介します。
『静かな退職という働き方』海老原 嗣生 著
「静かな退職」という最低限の働き方は、会社の生産性が下がり目標達成が難しくなることから、旧来の働き方に慣れた人間は納得しにくいものです。この「静かな退職」が非難されるべき働き方なのか、それともビジネスパーソンの「忙しい毎日」を変える新しい働き方となるのか。「静かな退職」が生まれた社会の構造変化を解説するとともに、管理職、企業側はどのように対処すればよいのかについて触れながら述べていく一冊。
『Quiet Quitting 静かな退職: 会社に残りながら最低限の仕事をするライフスタイル』羽端 康 著
企業目線ではなく、働く個人一人一人の立場から「静かな退職」の考え方を紹介しています。働き方、暮らし方、自己実現のやり方など、多様な価値観が大きく変化する現代において、自分らしいライフスタイルを見つけるヒントを与えてくれます。
まとめ:自分らしい働き方を見つけるために
「静かな退職」は、単なる「サボり」や「やる気のなさ」を意味するものではありません。
現代社会における働き方や価値観の変化を映し出す鏡であり、特に若手社員が自身の心身の健康やプライベートを重視する傾向の表れでもあります。
この働き方を選択するかどうかは個人の自由ですが、重要なのは、この選択が「自分らしい働き方」であるかどうか、自分らしい生き方に繋がっていくかを見極めること。
最低限の仕事をこなしながらも、責任感を持ち、周囲との良好なコミュニケーションを保つことで、仕事とプライベートのバランスを取り、充実した人生を送ることは可能です。
今回の「静かな退職」をきっかけに、自身のキャリアや人生について深く考え、より自分に合った働き方を見つける一助となれば幸いです。
関連記事
-

【副業で評判】ココナラの特徴を解説|ブログの仕事も依頼して、効率よく成果を出そう!
2025/11/23