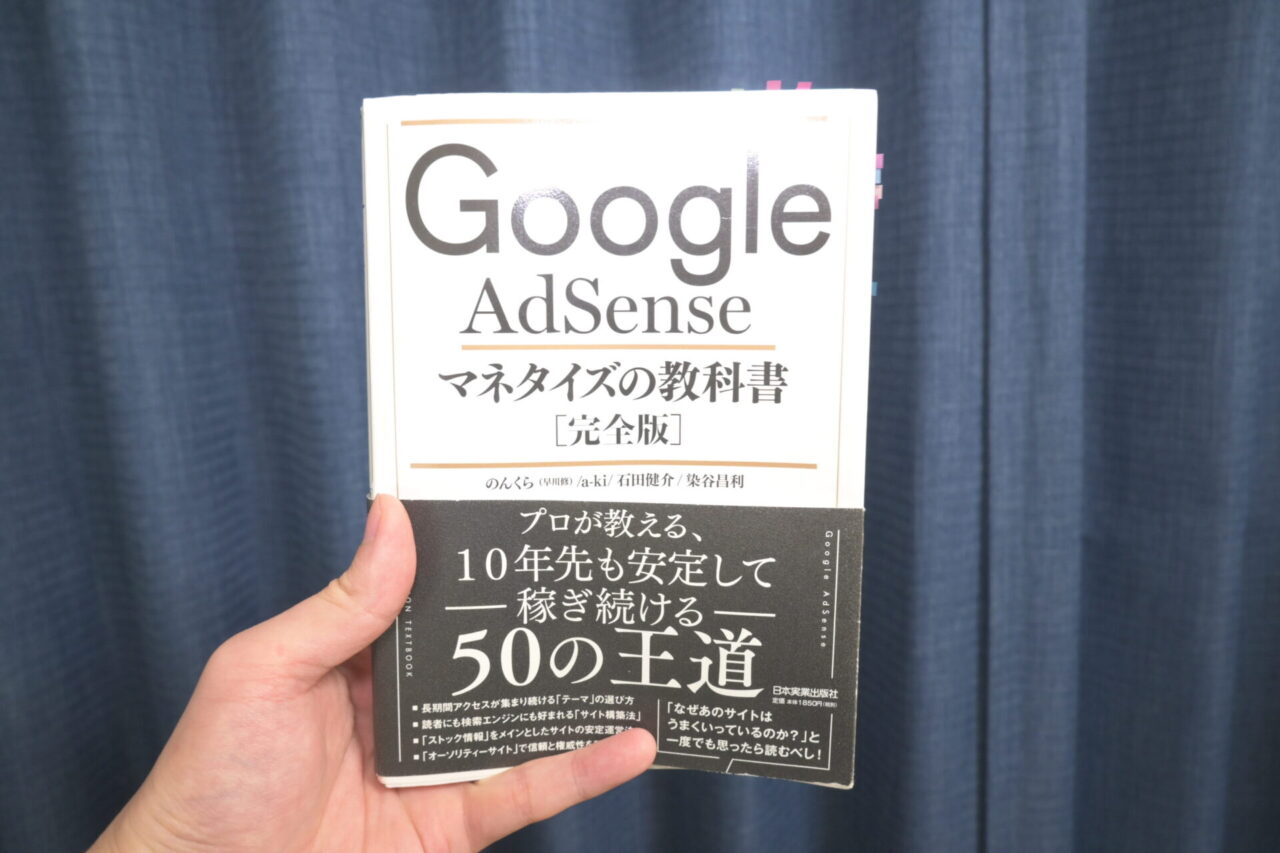こんにちは、たけもとです。
今回レビューする書籍「Google Adsense マネタイズの教科書」は、広くブログ界隈で評判となっており、聞いたことのある方も多いかもしれません。
私も執筆現在の1ヶ月前にアドセンスに合格したところで読んでみましたが、アドセンスの活用方法はもちろんのこと、質を重視したコンテンツを作り、読者に愛されるサイトを作る「心構え」にまで触れているような、学びの多い1冊でした。
アドセンスにこれから申請する方、合格してこれから運用を始められる方を中心に、ぜひ読んでみていただきたい書籍です。
書籍概要
著者について
著者はのんくら(早川修)氏、a-ki氏、石田健介氏、染谷昌利氏の4名
チャプターごとに担当者が分かれており、それぞれの方の経験・専門分野を生かす形で構成されています。
人数が4名と多いため詳細の説明は割愛しますが、アドセンスメインのブログで成果を大きく上げられた方、Google社内でアドセンス運用に携わっていた方、といった専門家が、本書の執筆をしています。
本の概要
「Google Adsense マネタイズの教科書」は、普遍的・王道なアドセンスの活用方法を学ぶことができる1冊です。
本書で掲示されている伝えたいテーマが、以下になります。
末永く使われ続けるサイトだけが習得できる「マネタイズの王道」
表紙帯に書かれている「10年先も安定して稼げる」というフレーズも印象的ですが、王道(=普遍的なこと)を徹底して行うことで、長い間さまざまなユーザーに愛されるサイトを作ろう、というのが基本的なスタンスです。
アドセンスでは、一朝一夕に大きな額面を稼げる魔法のような攻略法はありません(どのビジネスでも同じだと思いますが)。単に稼ぐ、のではなく「稼ぎ続ける」という目線で、アドセンスを使うサイトを構築していくうえで欠かすことのできないエッセンスが書かれています。

着実、王道、普遍的、といった語が、本書のキーワードになります。
ポイント整理
以下、書籍内の要点となるところについて、整理します。
本書のポイント
本書のポイントは以下のとおり。
・SEO戦略でアクセス数を安定させる
・読者にも検索エンジンにも好まれるサイトの構築
・「稼ぎ続ける」ためのアドセンスの運用
・オーソリティーサイトで信頼と権威を積み重ねる
この4つのポイントに従って、本書の内容について触れていきます。
SEO戦略でアクセス数を安定させる
どんなブログ書籍でもSEOについて触れていますが、本書でも同様に、クリック率の上げ方やキーワード設定等について触れています。
そんな中、「最大のSEO対策」として重要なポイントとして、サイトの即離脱を防ぐことが強調されています。
離脱率についてまず、ユーザーが記事を読んだ時の対応は、下記のようになります。
・記事内容に満足した →画面を切る(セッションを閉じる)
・記事内容に満足しない→検索画面に戻る
このユーザーの動きは、検索エンジンの評価方法や時代が変わっても変わらない、普遍的なことです。
検索画面に戻ることについては、Googleが「このコンテンツはユーザーが満足するものでない」と判断する要素となるため、ユーザーを満足させて、セッションを閉じる形で完結させたい。そのためには、Googleでなく、あくまでユーザーを向いてコンテンツを作ることが重要な視点になります。

ユーザーファーストの目線は、いつでも忘れないようにしたい…!
そのために、例えば、タイトルや冒頭部分でユーザーが探している答えを示す、文字と背景を読みやすい色にする、などの細かな工夫が求められます。
また、検索意図を満たす記事作りで欠かせないのが、オリジナリティ。ほかの記事では書かれていない独自のコンテンツによってユーザーを満足させる(役に立つ・感動する)ことは、常に追い求めたい要素です。
読者にも検索エンジンにも好まれるサイトの構築
読者にもGoogleにも好まれる、となると上記のSEOと内容が似通ってくるのですが、この項でのポイントは、コンテンツの表示速度です。
表示速度が遅いと、ユーザーのイライラに繋がり、結果として上記の即離脱につながってしまい、Googleの評価も落ちる、という流れになります。
表示速度の目安は1~2秒。シビアな世界ですよね。
コンテンツの表示速度については、Googleが提供している「PageSpeed Insights」というページで確認できるので、まだ利用したことのない方は、一度ぜひ使ってみてはいかがでしょう。

スマホ・パソコンそれぞれで、表示速度が遅くなっている要因を教えてくれます
そして覚えておきたいのが「スピードインデックス」という語。
スピードインデックスとは、ページをスクロールしない範囲での画面表示が完了する時間のこと。要するに、ページのファーストインプレッションで、ユーザーが「ちゃんと表示されたな」と感じるまでの時間ですね。
例えば、ページ上部はテキスト中心にすると、ページ上部に画像を設けたときよりも、スピードインデックスが上がります。
「稼ぎ続ける」ためのアドセンスの運用
アドセンスはクリック時に高い収益が生まれますが、ネットに対する社会のリテラシーが底上げされたことで、クリックされる機会そのものが減っています。
これは読み手としての私たちでも感じるもので、広告を広告だと分かってクリックするのは、買いたい・知りたいとちゃんと認知したときに限られます。
そんな背景を踏まえて、主に触れられているのが「ネイティブ広告」。サイトのデザインになじんで、ユーザーの利用を妨げにくい点が評価されています。
その他、記事内広告やリンク広告、広告のおすすめの設置箇所や、レポートの活用方法などについて触れています。
オーソリティーサイトで信頼と権威を積み重ねる
オーソリティーサイトとは、特定のジャンルについて権威を持ったサイトのこと。
平たく言うと、「〇〇といえばこのサイト!」と思い出してもらえるようなサイトのことですが、こうして思い出してもらえるのは、ほかならぬユーザーからの信頼によるものといえます。
サイトがオーソリティー化すると起こること
・SNSやQ&Aサイトで紹介されやすくなる
・継続的に被リンクが増えて検索順位が上がる
・検索エンジンを経由せずアクセスされる(ブックマーク等)
専門的な情報を提供する→ユーザーの評価が上がる→よく読まれるようになる→サイト全体の評価が上がり、外部にも取り上げられるようになる…という良いサイクルを生むことができます。
そのためには、テーマは一つに絞る、時代が変わっても価値が変わりにくいテーマを扱う、等が重要になります。

よく言われる「専門ブログが稼げる」という話は、この権威・専門性に関わっているものといえます。
また、一次情報(テレビ・書籍・インターネット等)を集めたものが二次情報と呼ばれますが、記事を書く際には、他のブログなどの二次情報からでなく、あくまで一次情報から作成するべきと述べています。
一次情報から作ることは、情報の信憑性の高さ、そしてユーザーと視点を共有できるという意味で、ユーザーに寄り添った・共感した記事となり、結果として信頼に繋がっていきます。
レビュー・感想
感じたこと・考えたこと
全体的に、具体的で質が高い情報が書かれています。実態部分まで目に見えるかのような書かれぶりで、チャプターごとに担当者が分かれていることの強みが、はっきりと感じられる書籍です。
書籍の内容については、「王道」というテーマに則り、基本的なところだからこそ徹底して解説する、というスタンスが伺えます。
王道・普遍的・基本的…このような要素は、特に実績を上げている人であれば、まずもって実行しているポイントになります。だからこそ、誰もが取り組んでいるポイントができていないことで差が生まれる…というのは非常にもったいないことです。
著者たちのスタンスに通じますが、この書籍の内容は、コツコツ積み上げていくものです。1つ1つのアクションができるようになるその過程で、「王道」を理解することができ、アドセンス、ひいてはブログという広告業の仕組みを深く理解するのに適した1冊です。
読む上での留意点としては、2018年時点の情報であることを認識しておくことと、あくまでアドセンスを主体にしたサイト向けの本であること。アドセンスとアフィリエイトを組み合わせて使う、という方も多いでしょうが、本書にはアフィリエイトに目線を向けたトピックは含まれていません。
とはいえ、「ユーザーの離脱を抑える魅力的なコンテンツを作る」「読みやすいサイト構成を作る」といった、触れられているトピックの多くは、アドセンスというテーマの枠を超えて、ユーザーに読まれるために重要なものばかりです。
アドセンスがどんな存在なのか、どうすればアドセンスを使いこなせるか、を理解したい方におすすめの本ですが、最終的にアドセンスを使わないであろう方も、学びが多い1冊になるかと思います。
印象的だった部分
その他、印象的に感じたところを数点、具体的にピックアップします。
ハイブリッド型構造
書籍の中で、ブログ構造について3種類について言及されたうえで、その良いとこどりをした「ハイブリッド型構造」について勧められていました。
ハイブリッド型構造とは、まとめ記事から派生するように、細分化された詳細記事を配置する、というサイト構成です。これまでも「トピッククラスターモデル」という語で、同様のサイト構成に触れて実践していましたが、それをより詳細に、他の構造と比較して説明されていたので、より学びが深まったと感じています。
今後のサイトづくりのなかで、より重視したいと思うポイントです。
モバイル対応は非常に重要
インターネットの利用状況についての概況が以下。
インターネット利用環境(2018年)
・スマートフォンのみ:48%
・スマートフォン+パソコン:38%
・パソコンのみ:5%
2018年で上記のような結果なのですから、2025年の現在は、よりスマートフォン寄りにシフトしているはず。ページの表示速度、コンテンツの表示のされ方や利便性など、スマホからアクセスする割合は想像以上に高い!というのを常に意識しておきたい。
Adsense以外の広告の選択肢
自動広告のうち、ブログ記事本文でなく、画面に覆うように表示される広告をオーバーレイ広告、といいますが、そのなかの「アンカー広告」について触れている箇所にて。
アンカー広告はユーザー体験とのトレードオフで収益を上げるもの、という前提のうえで、アドセンス以外の広告サービスについて触れられていました。挙げられていたサービスは(アンカー広告において)アドセンスよりもCPMが高いということで、内実がとても気になりました。
この点に限らずですが、アドセンスが自動広告の権威的存在であるものの、アドセンス以外の選択肢というのもあるわけで、関連情報も調べてみようと思った箇所でした。
おすすめの方
おすすめの方
・アドセンスに対しての理解を総合的に深めたい方
・ブログで、アドセンス含め広告の扱いについて学びたい方
・コツコツと実践、改善をしていくことに抵抗がない方
(書籍のスタンスがそうなのと、書籍の情報量自体も多い)
まとめ
以上、「Google Adsense マネタイズの教科書」のレビューでした。
どの書籍でも言われているように「ユーザーファーストの姿勢が前提になる」ことを踏まえて、アドセンスの活用方法について解説している書籍です。
アドセンスをこれから使い始める、アドセンスを使って稼ぎたいといった方を対象に、アドセンスの扱い方について深く学べる良書でした。
それでは、最後までご覧いただき、ありがとうございました。
関連記事
Kindle Unlimitedで対象書籍は読み放題!
アドセンスに合格したときの記録